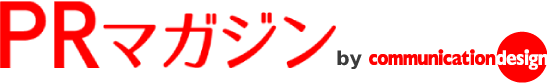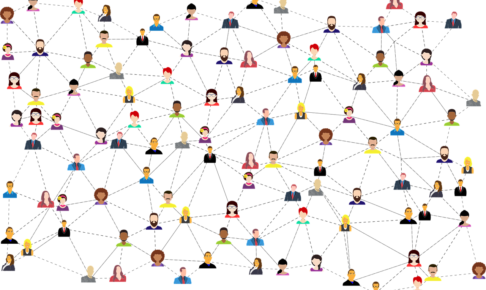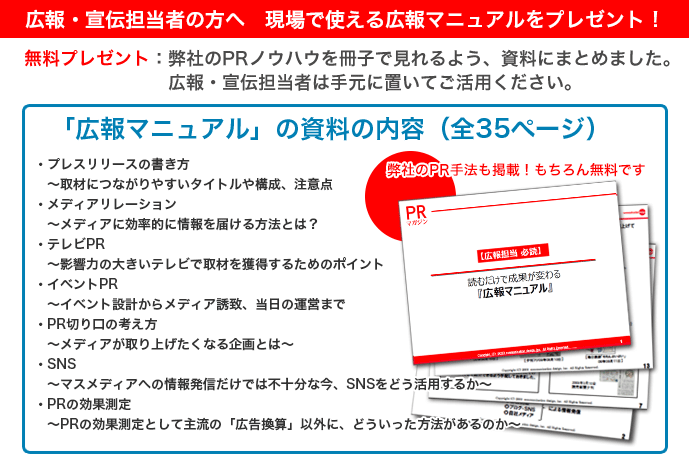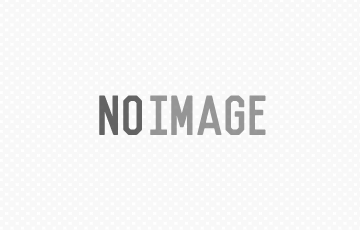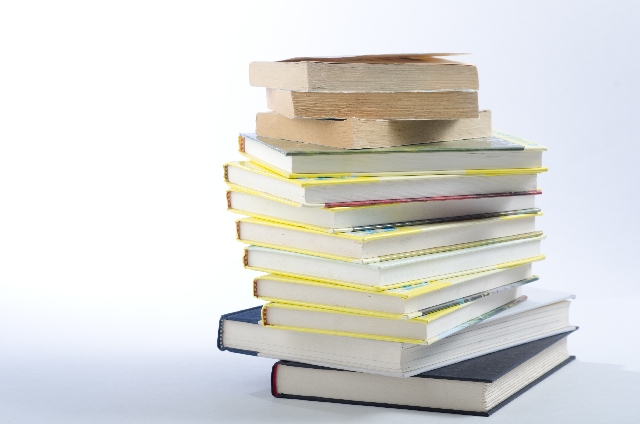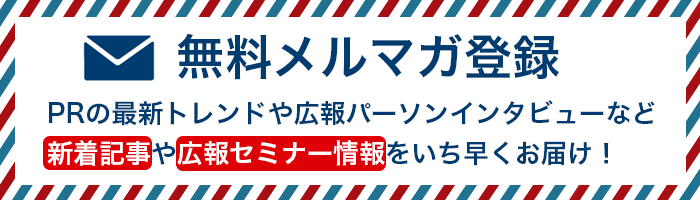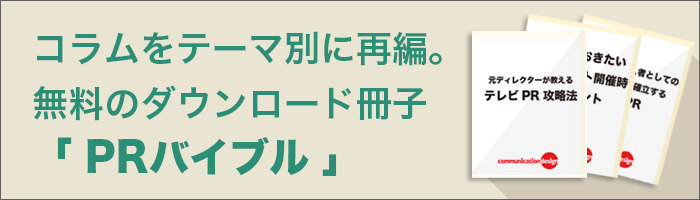SNS、院内掲示、公式ブログなどを通じた「専門家による情報発信」が、地域での信頼構築や新たな患者の獲得に効果的であることは、クリニック経営でも広く認識されるようになってきました。一方で、日々の診療に追われる中、「何を」「どう発信すればよいか」で悩む院長や広報担当者も少なくありません。
今回は、夏の健康情報の選び方を軸に、診療の現場から読み解く“患者ニーズ”の見つけ方、発信を続けるための現実的な工夫まで、クリニック広報に役立つヒントをお届けします。
この記事の目次
「熱中症だけじゃない」8〜9月に患者の関心が高まる健康トピックとは
夏の健康情報といえば「熱中症」や「脱水症」が定番ですが、患者の体調や生活の変化に目を向けると、他にも注目すべきテーマが数多くあります。
夏の終わりに増えるのが、胃腸の不調や慢性的な疲労感。冷たい飲食物や冷房による自律神経の乱れから、「夏バテ」や「睡眠の質の低下」を訴える声が増えてきます。
暦の上では立秋を迎える8月中旬ですが、実際の暑さは9月に入っても続きます。この時期にこそ、“秋バテ対策”としての生活習慣や体調管理をテーマにした発信が有効です。
まず、夏の疲れが蓄積し、自律神経の乱れや食欲不振、睡眠トラブルといった“秋バテ”の症状が出やすくなるのがこの時期です。また、子どもの夏休みが明けることで、生活のリズムが変わり、保育園・学校再開に伴う感染症への不安も高まります。こうした変化に寄り添った情報発信は、共感を得やすく、信頼感の構築にもつながります。
こうした状況の中で効果的なのが、「生活習慣」と「体調管理」をセットで伝える情報発信です。たとえば、「9月の睡眠不調、実は夏バテが原因?」といった切り口であれば、共感を得やすく、自然と対策への関心も高まります。
また、自費診療や栄養指導を行っているクリニックであれば、そこから派生した生活習慣テーマも立派な発信ネタになります。たとえば、栄養療法を取り入れているクリニックであれば、「更年期対策に必要な鉄分・亜鉛の取り方」など、自院の強みに関連するテーマも発信ネタになります。
注意喚起だけでなく、セルフチェックや簡単な対処法を添えることで、読者にとって「行動につながる」実用的な内容となります。
日常診療の中にある、“患者ニーズ”などから発信テーマを見つける方法
毎回テーマをゼロから考えるのは大変ですが、実はヒントは日常診療の中にあります。
・よく聞かれる質問
・スタッフが感じた小さな気づき
・待合室での会話や保護者の声
こうした“現場のリアル”こそが、患者ニーズの源です。たとえば、「最近この質問、多いな」と感じたらメモを取り、スタッフ間で共有してみましょう。簡単な「ネタ帳」や「質問リスト」をつくっておくだけでも、次回の発信がぐっと楽になります。
PR視点でのテーマ選定のヒント
ちなみに、PR会社の目線で企画テーマを考える場合、「メディアに求められるテーマは何だろう?」と、常にメディア目線を意識します。
その際に重要なポイントは、
「今年の夏、特に増えている症状は?」
「家族が体調を崩したときの対処法は?」
といった“生活の困りごと”からネタを広げていきます。
“意外と知られていない目からウロコの対処法”や、“そうそう、それで治った”
というようなあるある共感ネタ、
”こんな症状が出たら要注意!“
というような注意喚起ネタは、専門家だからこそ(エビデンスも確保できるので)企画として成立する土台があります。
情報発信の内容は、 “生活者が知りたいこと”を軸にする方が、読まれる確率は格段に上がります。診療を通じた患者との対話が、何よりの発信素材になるのです。
忙しい医療現場でも続けられる、発信の工夫と仕組みづくり
クリニック広報において、最も難しいのは「継続」です。特に、限られた人数・時間で運営される医療現場では、情報発信が後回しになりがちです。
そこで是非、取り入れたい事として、月ごとの「テーマカレンダー」を作成することをお勧めします。事前に3か月分程度の健康トピックをリスト化しておくことで、当月に「ネタがない」と悩むことが格段に減ります。
さらに、スタッフによる「患者の声」や「よくある質問」の記録も有効です。看護師・受付・栄養士など、立場によって異なる視点が加わることで、より多角的なテーマ選定が可能になります。
加えて、投稿や記事を“テンプレート化”しておくことも継続の鍵です。たとえば、「今月の院長コラム」「季節の健康チェックリスト」など、発信フォーマットを決めておけば、誰でも一定の品質で原稿を作成・投稿できるようになります。
また、SNSやブログで反応の良かった投稿は、院内掲示やLINEなどのSNS配信に再活用するのもおすすめです。コンテンツの“再編集力”を高めることで、少ない労力でも発信効果を最大化できます。
情報発信は「フォロワー数を増やすこと」が目的ではなく、「安心して相談できる存在」としての信頼を築く行為です。患者との関係を育む“診療外コミュニケーション”の一環として、無理なく続けられる体制を整えていきましょう。
【ニックネーム】カープマニア
【これまで担当した業界】IT、自動車、食品メーカー、飲料メーカー、自治体、
医療、家電メーカー、レジャー施設、金融、教育、他多数
【趣味】高校野球、広島カープ、川崎フロンターレ、ハワイ
【プチ自慢】両利き。お箸も野球もサッカーも、手足を左右同レベルで扱えます
多くご相談いただく内容とその解決方法をホワイトペーパーにまとめました。
PR切り口の考え方|メディアリレーション方法|広報KPIの考え方【無料ホワイトペーパー】
当社では新たなメンバーを募集しています!
PRコンサルタントとして活躍したい方はぜひご応募ください。
採用情報|PRの力で「社会問題」を解決する