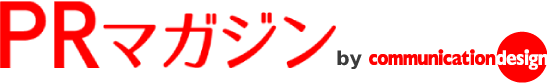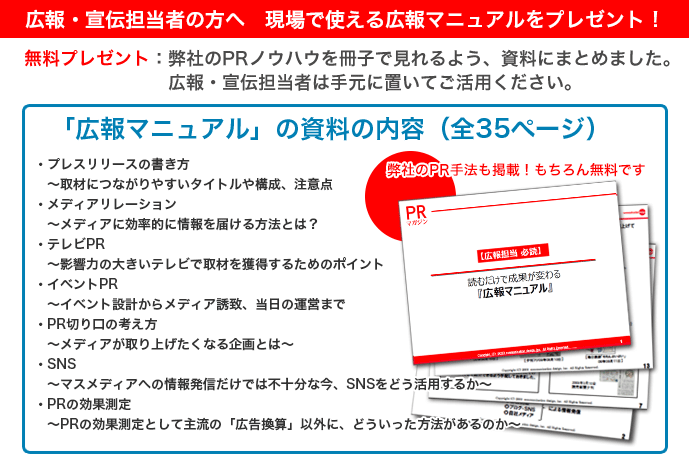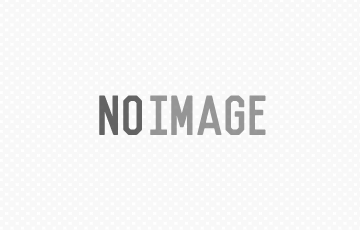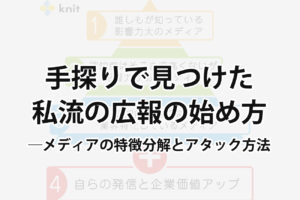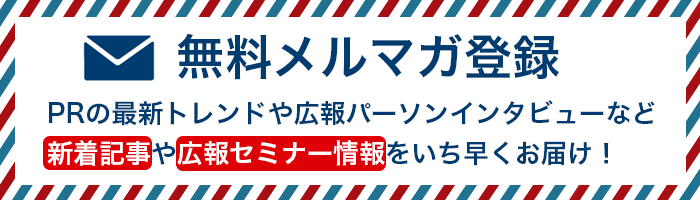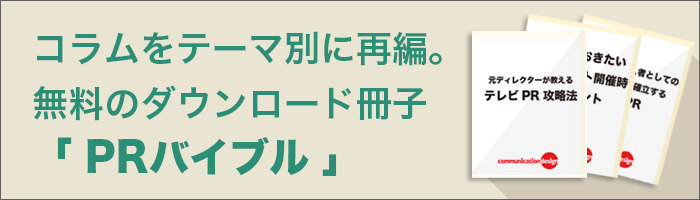「ビャンビャン麺」の“ビャン”という字を、あなたは書けますか?
画数は57画。あまりにも複雑で、一度見ただけでは到底覚えられない――それなのに今、この難読漢字「ビャン」は、日本中で知られる存在になっています。その認知の広がりには、単なる珍しさを超えた“仕掛け”がありました。
2024年のM-1グランプリでネタに使われ、大きな笑いを取ったことで再注目された「ビャンビャン麺」。ですが、そこに至るまでには、SNSでの拡散、テレビでの紹介、専門店の展開、そして「書いてみたい・話したくなる」仕組みがいくつも重なっていたのです。
この記事では、「ビャン」という一文字が“知る人ぞ知る”から“誰もが知る話題”になるまでの道のりをたどりながら、情報が拡散され、文化になるまでのプロセスを解き明かします。PRパーソンが明日から活かせるヒントも、きっと見つかるはずです。
この記事の目次
M-1グランプリで「ビャンビャン麺」のネタが観客にウケた
2024年末に開催された「M-1グランプリ」にて、とあるコンビが、次のような掛け合いを披露しました。(概要です)
え、そんな漢字ある?
漢字は”凛とした太郎”と書いて、しんにょう(⻌)でくくります。「ビャンビャン麺」方式。
これに対し、オーディエンスからは大きな笑いが起こりました。
私は、「昔はこんなにビャンビャン麺の「ビャン」の字はそこまで世間に認知されていなかったよな…」と思い、この字がどのように世間で認知度を上げていったのか、調べてみることにしました。
するとそこには、PRパーソンが学ぶべき題材がいくつか含まれていたので、ご紹介いたします。
かつては認知度が低かった「ビャン」の漢字―「ビャン」が全国的な認知を得るまでに起きたことー
そもそも「ビャンビャン麺」とは、中国・陝西省西安周辺の名物麺料理で、幅広の手打ち麺に辛味調味料を和えたものです。日本では2010年代後半から徐々に注目され始め、2020年代前半にはコンビニや大手チェーンも商品化し、現在では、M-1の例からもわかるように、「ビャン」という漢字が広く認知されるに至っています。
では、2010年代に何が起きたのでしょうか?このころ、中国の多彩な麺料理(刀削麺など)が日本でも注目され始めました。次第にビャンビャン麺にも目が向けられる土壌ができていきます。
2017年
転機の一つは2017年かと推測します。この年、中国を訪れた日本人ライターが現地のビャンビャン麺を食べ、その体験をウェブ記事にまとめました。
「画数が多すぎる漢字の麺料理」というユニークさに着目した記事で、日本のネット読者の関心を集めました。このようなネット発の情報発信により、ビャンビャン麺の存在が一部の好奇心旺盛な読者層に届き始めました。
2018年
2018年になると、日本国内でビャンビャン麺が実際に食べられるようになります。ビャンビャン麺の専門店も、東京都中央区にオープンしました。
幅広麺の独特な食感、そして、看板に大きく掲げられた難読漢字「ビャン」が話題を呼びました。お店側もこの漢字のインパクトを積極的にアピールし、グッズ販売なども行いました。
2018年頃から徐々に一般メディアも注目します。料理専門誌やグルメサイトがビャンビャン麺を「最新の中国B級グルメ」として紹介し始め、検索する人も増えていきました。2018年はまだ一部での盛り上がりでしたが、「世界一画数の多い料理名」というインパクトは確実に日本の好事家たちの興味を引き始めたのです。
2019年
2019年、ビャンビャン麺と「ビャン」の漢字は一気に全国区に知れ渡ることとなります。2019年9月放送のテレビ朝日系列のとある番組にてビャンビャン麺が特集されたのです。
番組内では「漢字が難しすぎる麺」として紹介され、出演者たちが実際に巨大な「ビャン」の書かれた看板を前に驚きつつ料理を味わう様子が放送されました。テレビにより、ビャンビャン麺は一気に“知る人ぞ知る”から“みんなが知る”料理へと躍進したのです。
加えてこの頃、とあるお笑い芸人が、難読漢字の覚え方を紹介する動画シリーズで、「ビャンの覚え方」を公開しました。
このようにバラエティ番組からネット動画まで、幅広いメディアで「ビャン」が取り上げられた結果、2019年末までにビャンビャン麺はかなり広範な層に知られるようになりました。
2020年
2020年にはさらにビャンビャン麺の認知が飛躍的に拡大しました。まず前述のビャンビャン麺専門店が店舗展開を進めました。メディアで話題になった影響もあり、これらの店舗には「一度あの麺を食べてみたい」という客が足を運びました。
このころ、コンビニでもビャンビャン麺が発売されました。発売直後から「コンビニにビャンビャン麺がある」とSNSで話題沸騰となりました。コンビニの商品は手軽に買えるため、これまで専門店に行けなかった層も含め一気に広まる結果となりました。
コンビニ展開に伴い、SNS上では「#ビャン活」というハッシュタグまで登場しました。「ビャン活」はビャンビャン麺を食べたり「ビャン」の字を書いてみたりするブームを指し、多くの人々が「書いてみたけど画数がエグい」などと投稿しました。料理としての美味しさだけでなく、「漢字を書けた・読めた」という体験も含めて楽しむ風潮が生まれたのです。
この後、大手外食チェーンもメニューで「ビャンビャン麺」を発売するなどして、さらに認知度を広め、現在に至ります。
以上の事象からPRパーソンが学ぶこと
もしあなたが「ビャンビャン麺」が認知されていない時期に、「ビャンビャン麺」を広く認知させてください、と言われたら、どのような施策を考えるでしょうか。
私であれば、ビャンビャン麺の歴史や、食べることによる人体への好影響(もしあれば)、などといった形で打ち出していっていたかなあ、、、と考えます。
しかし、今回は料理自体ではなく、「ビャン」という漢字にも焦点を当てることで、その認知拡大に繋がった、と捉えることが出来ます。
また、この一連の流れの中でSNSは、単なる情報拡散装置ではなく、“参加型の共感装置”になっていました。
「こんなに画数多い漢字、知ってる?」と投稿する人や、「書いてみた!」とチャレンジする動画、「読める?読めない?」と友達同士で話題にする、など…
こうして「シェアして楽しむ・人に教えたくなる」流れが生まれたことで、難読漢字「ビャン」は単なる雑学以上の存在になっていったのです。
このとき、SNSは「情報」ではなく「体験」を広める役割を果たしていたのではないでしょうか。
以上から学べることは、
・今の時代においても、テレビへの露出は知名度UPに大きな役割を果たすこと
・SNSにおいては、まだ広く認知されていない情報でも、「引っかかり」や「遊び心」があれば拡散の可能性は高いということ
・認知を広めるには、単なる発信だけでなく、共感や参加を促す形も有効であること
・現代のPRには、「人が自発的に関わりたくなる“場”をつくること」も有効であること
「ビャンビャン麺」の拡散は、情報拡散のエッセンスを体現した好例だったといえるのではないでしょうか。
【ニックネーム】らめにき
【これまで担当した業界】コンサルタント・健康・教育・DX・企業PR
【趣味】音楽鑑賞・野球観戦・バンド・ライブハウス・数学・ラーメン・カラオケ
【プチ自慢】「イントロドン」で半分以上0.5秒以内に正答できること
多くご相談いただく内容とその解決方法をホワイトペーパーにまとめました。
PR切り口の考え方|メディアリレーション方法|広報KPIの考え方【無料ホワイトペーパー】
当社では新たなメンバーを募集しています!
PRコンサルタントとして活躍したい方はぜひご応募ください。
採用情報|PRの力で「社会問題」を解決する