PRパーソンにおすすめ 本・メディア・雑誌(2023年 年末版)
広報PRパーソンに定期的なインプットは必要ですね。 最近のおすすめアイテムをご紹介させてください。 1.「先読み広報術 1500人が学んだPRメソッド」長沼史宏著(宣伝会議刊) 本著は、アステリア株式会社 執行役員コミュ…
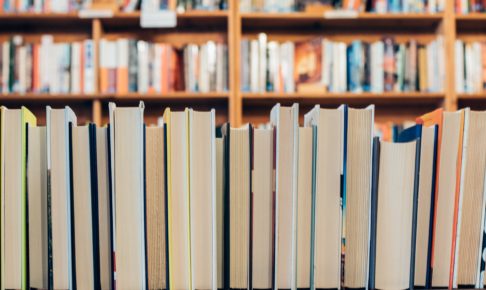 広報スキルUP
広報スキルUP
広報PRパーソンに定期的なインプットは必要ですね。 最近のおすすめアイテムをご紹介させてください。 1.「先読み広報術 1500人が学んだPRメソッド」長沼史宏著(宣伝会議刊) 本著は、アステリア株式会社 執行役員コミュ…
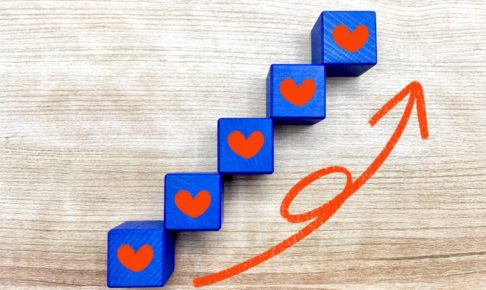 企業・人物PR
企業・人物PR
SNSの台頭で様々な情報が錯そうする今、ブランドの認知度を高め、新たな顧客やファンを獲得することが競争力を維持し成長を遂げるための重要な鍵となっています。 そこで企業は「ファンマーケティング」を積極的に活用してブランドの…
 広報スキルUP
広報スキルUP
皆さんはメディアリレーションで苦戦したことはありませんか? 「いつでも連絡が取れる記者がいればなあ」 「難しい企画だけど相談に乗ってくれる担当者がいればなあ」などなど、、、 PR広報を担当されている方であれば、誰でも一度…
 広報スキルUP
広報スキルUP
PRを行っていくにあたり、各種メディアと触れ合う中で、1つ1つの媒体に対し、媒体分析というものがありえますが、この広く広がったインターネットの世界で、やはりWEBから報道分析のネタを拾うという作業は、仕事の中心として存在…
 広報スキルUP
広報スキルUP
さて突然ですが、「ステルスマーケティング」(いわゆるステマ)をご存じでしょうか? 雑誌やTVなどのメディアからの発信に加え、インフルエンサーなどの個人に情報を発信してもらう「インフルエンサーマーケティング」も情報発信ツー…
 広報スキルUP
広報スキルUP
みなさんPR(広報)といえば何をイメージするでしょうか。分かりやすいもので言えば、プレスリリースの作成やメディアへのアプローチなどが思いつくかもしれません。 しかし、どんなに頑張ってもメディアに掲載されないということは起…
 広報スキルUP
広報スキルUP
広報PR活動において、しばしば大手メディアやテレビ、全国新聞などのメジャーメディアに焦点を当てがちで、場合によっては業界紙や専門誌は重要な役割を果たす媒体としては見落とされがちですが、実は非常に有効なツールとなり得る存在…
 広報スキルUP
広報スキルUP
広報の手法には、リリース配信やSNS運用、記者会見など方法は様々ですが、なかでも「取材」と「寄稿」がメディア露出の多くを占めると思います。 しかし「取材」となると毎月何本も連続的に獲得することは難しい場合が多く、メディア…
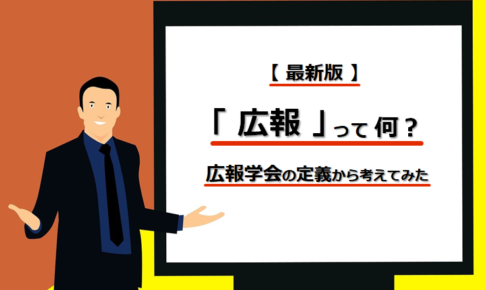 広報スキルUP
広報スキルUP
普段、弊社には広報・PRに関する様々な相談を寄せられています。 ・こういう商品があって、世の中に広めたい。 ・こんな人物がいるがメディアに出したい。 ・もっと自分たちの会社を有名にしたい。 ・メディアに出て採用力を上げた…
 広報スキルUP
広報スキルUP
「ウチの会社今の時期広報ネタがなくて、、」 広報担当者であれば、必ず通ったことのある悩みだと思います。 PRマガジンでもメディアリレーションに関する記事は多数あるのですが、今回は安定的にかつインパクトのある露出をどのよう…
 広報スキルUP
広報スキルUP
7月14日に公開された宮﨑駿監督 新作映画「君たちはどう生きるか」。 宮﨑監督にとって10年ぶりの新作だが、今回プロデューサー鈴木敏夫氏の「まっさらな状態で映画を観て欲しい」という考えから、映画の内容、出演者などの前情報…
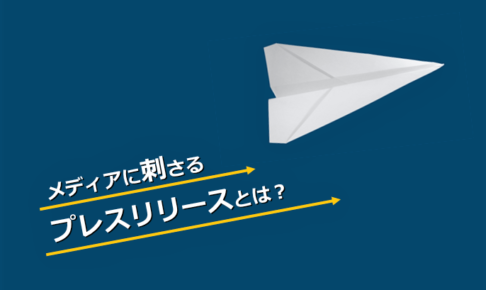 広報スキルUP
広報スキルUP
メディアに対して効果的なプレスリリースを発信するためには、裏話や思いを盛り込むことが重要です。裏話や思いを伝えることで、メディアや記者に魅力的なストーリーを提供し、共感を引き出すことができます。 今回は、社内の裏話や開発…
 広報スキルUP
広報スキルUP
今回は「書籍PR」についていくつか方法をご紹介したいと思います。 どうすれば書籍の購買につながるのか、著者のブランディングにつながるのか、少しでも皆さんのご参考になれると嬉しいです。 書籍PRにも色々な方法があると思いま…
 広報スキルUP
広報スキルUP
「この電車見送らないとかな」 コロナが5類に移行し、通勤電車は満員。街には人が増え、海外からの旅行客が確実に増えました。 パーソル総合研究所の研究結果によると、「自分の意図が伝わった」「相手の意図を理解できた」と感じる度…
 広報スキルUP
広報スキルUP
新型コロナウイルス感染症の法律上の分類が、季節性インフルエンザと同様の「5類」へ移行し、4年ぶりに脱マスクの夏がやってきます。 最近では、新製品発表イベント、セミナーなどのリアル開催やリアルでのメディアプロモートが増えて…
 広報スキルUP
広報スキルUP
あっという間に5月の連休も終わり、気づけば梅雨モードになってきていますが、皆様、体調は御変りありませんでしょうか。 さて今回は、競合プレゼンについて、企業内広報担当役員ならびに担当者の皆様に向けて、その要点をシンプルにま…
 広報スキルUP
広報スキルUP
4月から「初めて広報・PRの仕事に就いた」「広報部に配属された」なんて方も多いと思いますが、入社から一か月が経ちいかがでしょうか? 私は現在入社3年目のPRパーソンなのですが、タイトルに書いたとおり 「広報ってキラキラし…
 広報スキルUP
広報スキルUP
新年度に入り、広報担当者の中には「今年はよりメディアとの関係性を強くしたい」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回はそんなメディアとのコミュニケーション手法の1つ「メディアラウンドテーブル」について解説して…